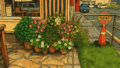35 一瞬の出会いを逃すな。相手の人物を見抜くことである。
【大川隆法 箴言集『コロナ時代の経営心得』より抜粋】
*・゜・*:.:*・゜・*:.:*・゜・*:.:*・゜
さて、私たち、幸福の科学の信者の幸福とは「悟りの幸福」です。私たちは、「正しき心の探究」を通して「愛と悟りとユートピア建設」をこの地上に実現するための使
命を仏から与えられ、その実現のためにすべてを既に与えられました。
ここで、お釈迦様の教えである仏教的精神を振り返り、私たちの幸福を全世界に述べ伝える原動力となすべく、ひきつづき教典『悟りの挑戦(下巻)』を共に学びます。経典をお持ちでない方はこの機会に是非ご拝受ください。【税込み1800円】
―本書をていねいに精読するならば、『悟りの挑戦』が、仏陀自身の仏教解説であることがわかることだろう―上巻「あとがき」より
*・゜・*:.:*・゜・*:.:*・゜・*:.:*・゜
■『悟りの挑戦(下巻)』第1章「中道からの発展」
3 ものの見方における中道
②断常の中道【※①は「白紙に戻せ」でした】
ただ、中道の説明は、もちろん、これにとどまるものではありません。もっともっと奥の深いものが、そのなかにはあるのです。
では、この中道の思想は、歴史的にはいかなるかたちで現われてきたのでしょうか。ものの見方、考え方における中道、価値判断における中道は、いかなる展開をしたのでしょうか。これを少々検討してみたいと思います。
さて、先ほど述べた実践的観点からの中道のことを「苦楽中道」といいます。「不苦不楽」―苦でもなく、楽でもない。「苦楽の中道」とよくいいます。
これに対して、ものの見方における中道とは、たとえば、一つには「断常の中道」といわれる考え方があります。「断」とは断つという意味です。「常」とは常なるという意味です。「断常の中道」という言葉があります。これは、別の言い方では、「不常不断の中道」ともいいます。この「断常の中道」とはいったい何かについて検討してみたいと思います。
これは、釈迦当時のインドでも、ずいぶん盛んに議論されていたことなのです。
当時、人間の自我のことを「アートマン」、天なる神霊的存在のことを「ブラフマン」(梵天)といい、梵天と各人の自我は「梵我一如」―本来ひとつのものであるという思想が主流でした。
確かに、魂の核なるものは神仏と同じ光であり、仏性を宿していますから、その仏性という意味において、天なる梵天(これは高級神霊ぐらいの意味である)と人間とは一体のものであるという、この伝統的なバラモンの考え方は、現代の私たちの考え方からいっても正しい考え方です。
しかしながら、この考え方が固定化してきたときにどうなるでしょうか。現実の世の中を見たときに、さまざまなる悪がなされています。ある者は殺人を犯し、ある者は窃盗を犯し、ある者は他人の妻を犯し、ある者は無軌道な人生を送り、ある者は一家を破産させ・・・と、いろいろな生き方をしています。
こうした現象というものを見たときに、そこに堕落する者、失敗している人間、敗残の人間があり、成功している人間があるのです。この違いというものを認めないで、単なる梵我一如という思想だけで押していったときには、人間は、自分の修行というものをなおざりにする、それを捨てる、いいかげんにする、そういう習性が発見されたわけです。
したがって、「自分の自我なるものが、こうした高級神霊とまったく同じものだという、ただそれだけのものの考え方はきわめて危険な考え方である。これに対して、何らかの反論をしなければならない」、当時の釈迦はこうした思想的立場にあったわけです。
しかしながら、釈迦は、人間は霊的な存在であり、今世(三次元世界)と来世(霊界)の間を往ったり来たりしている存在でもあるということを知っていました。そこで、次のような考え方をしました。
前述の「断常」の「常」―常なるものとは「人間の自我なるもの、己なるものは常住である。すなわち、ずっと続いていくものなのだ。そのままで続いていくものだ」という考えです。もう一つの「断」―断絶とは「人間は死を境として自我なるものを失っていく。死んだら自分というものは無くなる」という考え方です。こうした極端な考え方がありましたが、前者の考え方は、霊魂観に基づく伝統的なバラモン教学の考え方ですし、死ねば何もかも終わりになってしまうという後者の考え方は、当時も胚胎(はいたい)してきていた唯物論的な考え方の一つです。死ねば何もかも終わりだという考えは、現代にもかなり強くあります。この両者の考えに対して、釈迦は、「断常の中道」「不常不断」ということを言ったのです。
これは「人間というものは、死んだら何もかもなくなってしまうような存在ではない。そこにおいて『不断』―断ずることはできないものである。しかしながら、人間というものは、あなたが自分だと思っているものが、そのままずっと続いていくものでもない。これは決して、肉体が死なないということを言っているのではない。肉体のなかに宿っている私という存在は、霊界に行ったら、まったく同じものではないということを言っているのだ」ということです。
要するに、この世で自分だと思っているいろいろな考え方は、眼・耳・鼻・舌・身・意の六根を中心として発生している自我論なのです。目で見、耳で聞き、鼻でかぎ、口で味わい、手で触れるなど、こうした六根を中心としてさまざまなる判断をし、考えて、自分なるものを「有る」と考えている、この我が、来世もまったく同じく続くかと思ったら、そうではないのです。
あの世の生命があるということは、今あなたが自分だと思っているものが、そのままあの世に往くということではありません。そのような感覚器官というものはなくなります。そして、もっと精妙なる「霊体」という身体になって、あの世に渡っていきます。また、霊体になったときは、最初、人間と同じような五体を持った姿で生活していますが、やがて霊界の生活に慣れていったときに、そのような姿をとらずして生活することができるようになってきます。
そうすると、あなたが自分だと思っている形態や姿は、ほんとうのあなたではなく、あの世に還ったあなたは、自由自在な存在となります。あなたという存在自体は継続しますが、今のあなたとは違うあなたになってしまいます。
そうすると、「あなたの自我、あなた自身というのは、ずっと続くのだ」という「常住」―常なるという考えと、「あなたは死んだらそれで終わりだ」という考えの両方が、正しいことではなくなります。
ゆえに、「この両方の考えは真実ではない。この中道に入らなくてはならない」、こういうことを説いていたわけです。これが「常断の中道」という考えなのです。
【大川隆法『悟りの挑戦(下巻)』第1章『中道からの発展』より抜粋】
*・゜・*:.:*・゜・*:.:*・゜・*:.:*・゜
さて、ここからは、「幸福の科学」の原点に立ち返り、幸福の科学が全世界に広げようとし
ている教えを共に再確認させていただきます。幸福の科学に入会・三帰されて間もない方や、これから、新しい方を伝道するに当たって、幸福の科学の教えをどのようにお伝えしたらよいのか。ヒントになれば幸いです。基本三部作の『太陽の法』を引用しながら、幸福の科学の教義を共に学びます。なお、経典『太陽の法』は、光とは何か。仏法真理とは何か。という問いに答える幸福の科学の教えの基本です。経典をお持ちでない方は、是非この機会に拝受ください。【税抜2000円】
*・゜・*:.:*・゜・*:.:*・゜・*:.:*・゜
■『太陽の法』第3章「愛の大河」
8 愛と八正道
私は、第2章で、真説・八正道を説きました。そしていま、愛の発展段階説を論じました。そこで、これからこの両者の関係について話してみたいと思います。
真説・八正道のなかでは、人間として正しく生きてゆくための八つの道があることを話しましたが、これもまた、日々の悟りの材料であり、悟りへの道なのです。一方、愛の発展段階説では、修行の対象として、「愛する愛」「生かす愛」「許す愛」「存在の愛」の四段階があることを説きました。
この両者をくらべてみると、八正道のほうは、日々の修行であり、日々の悟りを重視しているのだといえます。そして、愛の発展段階説は、日々の生活に端を発しながらも、ある程度、中期、あるいは、長期的な目標もあわせもっていることが指摘できると思います。
八正道による悟りへの道を、あえて愛の発展段階説による悟りへの道とくらべるならば、つぎのことがいえるでしょう。
一 正見、正語は、愛する愛に通じる。
二 正業、正命、生かす愛に通じる。
三 正思、正精進は、許す愛に通じる。
四 正念、正定は、存在の愛に通じる。
そこで、それぞれがどういうことかについて、その意味を説明していきましょう。
まず、なぜ正見、正語は、愛する愛に通じるといえるのでしょうか。愛する愛とは、自分が当然関心を持つべき対象に対する愛です。そこで、相手に対して、適切なる好意をもつためには、まず、正しい信仰に照らして、相手を正しく見ることからはじめなければなりません。ものごとの正邪を見分けることが大事です。また、相手が、いま、何を欲しているのか。いま、相手がこまっていることはなんなのか。それを先入観を排して、ありのままに正しく見ることです。正しく見ることができたら、今度は、正しく語ることです。つまり、相手に対して、有害な言葉ではなく、適切なアドバイスをする。相手の心をあたたかくするような言葉、こまっている相手を立ち直らせるような適切な言葉を使うことです。
つぎに、正業、正命は、生かす愛に通じます。正業とは、正しく行為すること。釈迦の時代には戒律を守り、身体が罪を犯さぬようにすることを意味しました。
つまり、人間を含め、生き物を殺したり(殺生)、ものを盗んだり(偸盗・ちゅうとう)、夫あるいは妻以外の異性と色情関係をもつこと(邪淫・じゃいん)を戒めていました。現代に翻訳するなら、暴力、盗み、不倫等を避けて、社会人としての倫理性を高めることです。また他人の人の人権や人格を十分に尊重して行動することです。自己の社会人としての品性を陶冶していくことによって、他の人々をも啓蒙していくことができます。
正命とは、自らの生命を正しくまっとうすること、すなわち、正しく生活することです。仏法真理に反する、自らを堕落させるような職業選択(暴力団、犯罪性を帯びた風俗営業、無用の殺生を生業とすることなど)を避け、大酒、賭けマージャンなどの賭博行為、競馬や競輪への狂奔、麻薬、健康を害する喫煙等からも遠ざかるべきです。多額の借金生活を余儀なくされ、サラ金等に追われる生活も、正しい生活とはいえません。また人間は、自分ひとりだけで生きてゆくことはできません。さまざまな人に助けられて、さまざまな人とともに、共同生活をし、生かしあっております。すなわち、正しい生活、つまり、正しい信仰生活のなかにこそ、生かしあいがあり、生かす愛の実践の場があるのです。お互いに導きあうべき場がある・
・です。言葉をかえれば、家庭ユートピアづくりに励む人、つまり、正命実践者が増えれば、増えるほど、この世は天国に近づくのです。かくして、正業、正命は、主として、生かす愛の段階にあるといえます。
第三に、正思、正精進は、許す愛に通じます。まず、正思―正しく思うということ、つまり、心の三毒(貪・瞋・癡)や六大煩悩(三毒に慢・疑・悪見を加える)に振り廻されず、人間関係を真実な眼で見て、調整しようという思いが、この正しく思うということなのです。相手の現象人間としての姿にまどわされず、実相世界の住人としての真実なる姿を心に描き、その人間との正しい関係の在り方を考えます。自分の心の内にまちがった考えがあればそれを反省します。そしてお互いに仏の子同士として、本来のあるべき姿を思います。そこにはともに導きあいつつ、大調和をめざす人々の姿があります。正しく思うということができれば、心は常に寛容で、あらゆるものをつつみ込むような、豊かな気持ちになれます。だから、この・
・地を磨き上げれば心は自然に、許す愛の境地へと高まってゆくのです。
正精進もまた、同じです。正精進―正しく道に精進するということは、仏法真理の獲得のために努力、邁進するということであり、誘惑を断ち、善念で心を満たした結果、日々に悟りの境地が深まってゆくのです。仏への道に対して、正しく精進するとき、徳力は倍加され、そこには怒りなく、そこには愚痴なく、そこには不平不満なく、そこにはねたみなく、文字通り「正思」の生活が実現し、ただ大調和の世界が地上に湧出するのみです。すなわち、心は、つねに不動心をたもち、罪ある人をも、清めるだけの力が出てくるのだといえます。ですから、正精進に磨きがかかれば、かかるほど、宗教的見識が一層深まり、まさしく、許す愛の境地はひろがってゆくのです。
そして、第四の正念、正定とは、存在の愛へ通じます。正念とは、正しく念ずること、つまり仏法真理の生活に心を集中させることです。心を落ち着けて正しく自分の未来設計をなし、正しき自己実現の姿を祈る。これが正念です。ところで、仏法真理を求めている者にとって、正しき自己実現とは、何を意味するのでしょうか。それは、仏の子人間としての完成した姿をあらわします。仏と一体の境地、すなわちこれ、如来の境地です。人間として最高の姿、そして、その人の存在自体が、世の人々の尊敬の対象であり、その人の存在自体が、世の人々に対する光明であるような人間となること。それが正しく念じるということであり、正しき人生目標の究極の姿だといえます。
また、正定―正しく定に入るということ、正しい瞑想状態に入ることは、宗教者として、仏法真理を求める者としては、最高段階の姿なのです。古来、宗教家たちはヨガだとか、座禅だとか、止観だとか、あるいは、反省的瞑想だとか、さまざまな精神統一をして、高級諸霊との交流を求めました。まず、正定には、日々の反省のなかに、自らの守護霊と交流する段階があります。さらに天命を遂行すべく、指導する霊との交流があり、最終段階として、上段階光の指導霊、如来界の人々と交信する段階があります。
生きている人間の心は、一念三千。如来の境地の悟りを得れば、正定のなかで、如来界の大指導霊との交流が可能となります。肉体をもった八次元の方で、上段階の光の大指導霊から、直接、あるいは、間接の指導を受けていない人はひとりもおりません。最低限であっても、インスピレーションを受けて、自らの天職を遂行している。それだけは、確かです。
結論としていえば、存在の愛の段階に到達するには、正しく定に入り、解脱すること、そして、正しい精神統一を完成するということが前提となります。
以上に述べてきたことは、言葉を換えていうならば、八正道には、修行としての段階があり、正見・正語→正業・正命→正思・正精進→正念・正定と四段階にわけて修行にはげむと反省がしやすいということです。これは釈迦の説いた八正道の順序とは異なりますが、初学者にとっては有効な修行順序です。
このことは、すなわち、愛する愛ができるようになったら、つぎに生かす愛の実践にはげみ、生かす愛の段階を経て、許す愛の段階にいたり、最終的には、存在の愛に達するというのと、同じだといえます。
正見・正語なくして、正業・正命はなく、また、正思・正精進、正念、正定もありえません。同じように、愛する愛なくして、生かす愛も、許す愛も、存在の愛もありえないのです。いずれにせよ、まず、最初の段階がもっとも大切だということです。
【大川隆法『太陽の法』第3章「愛の大河」より抜粋】
*・゜・*:.:*・゜・*:.:*・゜・*:.:*・゜
続きまして、幸福の科学の基本三法の一つ、経典『永遠の法』を振り返ります。
人生の真理を網羅した、法の巨大な体系【※太陽の法】、数千年以上の視野をもって、諸如来、諸菩薩たちの活躍を語る時間論【※黄金の法】、そして、この世を去った実在界の次元構造を明確に説明し尽くす空間論【※永遠の法】、その三本柱が、エル・カンターレの法を特徴づけるものです。本書は、『太陽の法』(法体系)、『黄金の法』(時間論)に続いて、空間論を開示し、基本三法を完結する目的で書き下ろしたものです。これでエル・カンターレの法の輪郭が見えてきたことでしょう。―まえがき―
*・゜・*:.:*・゜・*:.:*・゜・*:.:*・゜
■『永遠の法』第2章 五次元の世界
6悲しみと苦しみ
さて、昔から、「天国は永遠の楽園であって、悲しみや苦しみがない」と言われていますが、「地獄以外の四次元や、五次元世界に還ってくると、悲しみや苦しみというものは、事実上、消え去ってしまって、存在しないのかどうか」ということが問題となります。この点につて話をしていきましょう。
普通は、「悲しみや苦しみは地獄特有のものであって、天国にはない」と言われています。それでは、人間が涙する、つまり泣くということを仏はもともと予定していなかったのでしとょうか。あるいは、天国にいる人は笑うことしかできないのでしょうか。こうしたことについて考えてみましょう。
「喜怒哀楽は人間の基本的な感情である」ということは否めないと思います。喜怒哀楽、すなわち、喜び、怒り、悲しみ、楽しみ、こうした感情は基本的にあると言わざるをえないのです。
たとえば、喜びの反対にあるのは悲しみでしょうが、悲しみは喜びの不在かといえば、それだけでは説明がつかないものがあります。
昔から一元論と二元論の争いがあって、一元論の立場からは、「悪は善の不在である」「寒さというものはない。それは熱の不在で、暖かさの不在である」というような言い方をします。アメリカの光明思想家でニューソートの草分けの一人であるエマソンも、そのように考えていたようです。
確かに、これは一面ではあたっているのです。寒さは熱の不在であり、悪は善の不在でしょう。しかしながら、それだけでは説明できない何かがあるわけです。
悲しみは涙をともなうものですが、涙が出るという現象は喜びの不在かと言えば、必ずしもそうとは言えません。喜びがないだけでは、涙が流れることはありません。やはり悲しみというものがあることを、みなさんは知らねばならないのです。
次に、楽しみの反対である苦しみという感情があるかないか、楽しみのみが実在で苦しみは実在しないのか、楽しみがないところに苦しみがあるのか―こうした問題についても考えてみましょう。
苦しみというものも、やはり、ないわけではないのです。たとえばテニスなどのスポーツをして、一時間や二時間、汗を流した後は、さわやかさ、爽快感を感じします。しかし、その前には汗を流すという現象があったことは事実です。そうした肉体的な疲労感が、その後の爽快感につながっているのです。
このように、この世とあの世の大部分には、二元的なるものがあると言わざるをえません。究極の仏が、光一元であり、善一元であり、愛一元であって、善きものでしかないとしても、仏が三次元の地上界や四次元、五次元という下位霊界を創ったのは、魂の進歩、向上というところに主眼があったのです。
魂の進歩、向上は、相対の世界においてもたらされことが多いのです。お互いに切磋琢磨し、磨き上げることがなければ、向上することはなかなか難しいものです。一元論の世界、つまり喜びしかないという世界は、素晴らしいように見えても、ある意味では、ぬるま湯的な世界であることも事実でしょう。
そうした理由から、仏は方便として、悲しみや苦しみと思えるものを、地上界や下位霊界において与えているのです。
たとえば、五次元善人界の人であっても、自己実現が困難に感じられることがあります。五次元の人も地上の人と同じように祈りをしているのですが、その祈りが充分にかなう場合と、それほどかなわない場合とが、やはりあるのです。
彼らにとっては、自分の祈りが正しい祈りかどうかが、なかなか分からないのですが、上位にある霊から見れば、その祈りはまだかなうべきではないという場合があるわけです。
そして、彼らの祈り、すなわち念いが実現しないときには、ある程度の悲しみや苦しみを伴うのは事実です。したがって、彼らも魂の足腰を鍛えているということができるのです。
【大川隆法『永遠の法』第2章「五次元の世界」より抜粋】
*・゜・*:.:*・゜・*:.:*・゜・*:.:*・゜
本日の学びは、日々の修行項目である「真説・八正道」と、中・長期的な修行項目である「愛の発展段階説」をつなぐ内容でした。
主から教えていただいた正しき心の探究としての心の修行は、八正道のほうは、日々の修行であり、日々の悟りを重視しているのだということ。そして、愛の発展段階説は、日々の生活に端を発しながらも、ある程度、中期、あるいは、長期的な目標もあわせもっていることを教えていただきました。
「八正道」と「愛の発展段階説」との関係については、やや難しい区分となりますが、このようになります。
『八正道による悟りへの道を、あえて愛の発展段階説による悟りへの道とくらべるならば、つぎのことがいえるでしょう。
一 正見、正語は、愛する愛に通じる。
二 正業、正命、生かす愛に通じる。
三 正思、正精進は、許す愛に通じる。
四 正念、正定は、存在の愛に通じる。』
そして、結論としてこのようにも説かれています。
『結論としていえば、存在の愛の段階に到達するには、正しく定に入り、解脱すること、そして、正しい精神統一を完成するということが前提となります。
以上に述べてきたことは、言葉を換えていうならば、八正道には、修行としての段階があり、正見・正語→正業・正命→正思・正精進→正念・正定と四段階にわけて修行にはげむと反省がしやすいということです。これは釈迦の説いた八正道の順序とは異なりますが、初学者にとっては有効な修行順序です。』
このように、現代の四正道のうちで、とくに、「愛」と「反省」を結び付けて毎日の宗教修行を行うことを主は私たちに勧めているわけです。ここは仏法真理の教学上とても重要な論点であると言えます。
以下、真理用語の解説を引用します。
●心の三毒と六大煩悩
仏性をけがす三つの悪しき精神作用(煩悩)を心の三毒といい、むさぼりの心(貪・とん)怒りの心(瞋・じん)、愚かさ(癡・ち)を代表とする。これにうぬぼれの心(慢・まん)、疑いの心(疑・ぎ)、種々の間違った見解(悪見・あっけん)の三つを加えて、六大煩悩とし、人間の正しき思いを迷わせ、地獄へ墜とす重大原因と考えるのが、仏教的正思の基準である。ただし、百八煩悩といわれるほどに、悪しき精神作用は多く、正思には無限の深まりがある。
このように八正道は、仏教の奥義とも考えられる重要な教えである一方、取り組むのが難しいところがあります。ぜひとも、日々の反省行は、『仏説・正心法語』の五番目の経文『仏説・八正道』を繰り返し読誦しながらともに取り組んでまいりましょう。
後半の、『永遠の法』では、この世界は一元論か二元論か、という問題について、かなり重要な教えが織り込まれていました。
『この世とあの世の大部分には、二元的なるものがあると言わざるをえません。究極の仏が、光一元であり、善一元であり、愛一元であって、善きものでしかないとしても、仏が三次元の地上界や四次元、五次元という下位霊界を創ったのは、魂の進歩、向上というところに主眼があったのです。
魂の進歩、向上は、相対の世界においてもたらされことが多いのです。お互いに切磋琢磨し、磨き上げることがなければ、向上することはなかなか難しいものです。一元論の世界、つまり喜びしかないという世界は、素晴らしいように見えても、ある意味では、ぬるま湯的な世界であることも事実でしょう。
そうした理由から、仏は方便として、悲しみや苦しみと思えるものを、地上界や下位霊界において与えているのです』
この世の中に、多くの二元論的な対立があるのは、根本仏がこの地球を魂の修行場として設計しており、霊的な人生観の向上―悟りの向上―を期待してつくられた舞台装置であることが分かります。人生に苦難や困難や、真剣な祈りがかなわない事にも、大きな視点から見れば、魂を鍛え、育むためであることを私たちは自らの人生のなかでも読みとらなければなりません。
*・゜・*:.:*・゜・*:.:*・゜・*:.:*・゜
本日も、皆様とともに主の新復活を祈り続けてまいります。
*・゜・*:.:*・゜・*:.:*・゜・*:.:*・゜
Lord EL Cantare is my All. 主こそ私のすべて。
We are One, with our Lord. 我々は主と共に一体である。
One for All. All for The One. 一人は主のため、隣人のために。みんなは主の悲願のために。
*・゜・*:.:*・゜・*:.:*・゜・*:.:*・゜
■□■□■□■
。゜+. With Savior 。゜+.
100%エル・カンターレ信仰
―天御祖神とともに―
伊勢から世界に伝える強い信仰
■□■□■□
E-mail:ise@sibu.irh.jp
□■□■□
https://hsise.com/
□■□■
TEL:0596-31-1777
■□■
FAX:0596-31-1778
□■
文責:蒲原宏史
■
(10/22-1)【基礎教学通信】295『太陽の法』を読む28「愛の大河」愛と八正道―「悟りの挑戦(下巻)」断常の中道―『永遠の法』悲しみと苦しみ
 『太陽の法』
『太陽の法』