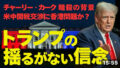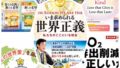96 最後は、会社が他人の手に渡るか、つぶれるかだと、肚をくくれ。
99 自分がこの世を去ってから後のことを遠望せよ。
【大川隆法 箴言集『仕事への言葉』より抜粋】
*・゜・*:.:*・゜・*:.:*・゜・*:.:*・
さて、私たち、幸福の科学の信者の幸福とは「悟りの幸福」です。私たちは、「正しき心の探究」を通して「愛と悟りとユートピア建設」をこの地上に実現するための使命を仏から与えられ、その実現のためにすべてを既に与えられました。
ここで、お釈迦様の教えである仏教的精神を振り返り、私たちの幸福を全世界に述べ伝える原動力となすべく、教典『悟りの挑戦(上巻)』を共に学びます。経典をお持ちの方はこの機会に是非ご拝受ください。【税込み1800円】
*・゜・*:.:*・゜・*:.:*・゜・*:.:*・゜
■『悟りの挑戦(上巻)』第2章「無明からの脱却」
7『こころ』にみる五毒
以前、テレビのドラマで、たまたま夏目漱石の『こころ』を観たことがあります。この作品は、学生時代に小説で読んだことがありますが、文章もきれいでしたし、そのときには非常に文学的な感動を覚えました。しかし今、真理を学び教える立場にたって、もう一度そのようなドラマを観てみると、とても不思議な感じを受けたのです。
内容については、知っている方もおそらく多いでしょう。
まず、主人公が「先生」と称する初老の人に出会います。「先生」は教養のある人で、主人公が「先生」のもとに通っているうちに、「先生」が「実は自分には苦しい過去がある」という話を始めるのです。
その内容は、最後に遺書のかたちで残されます。
それによると、「先生」は学生時代に、ある未亡人のところに下宿していましたが、そこのお嬢さんに恋をします。そのときに、お寺の息子のKという学友が、医学部から文学部に転部したことで親から勘当され、学費がなくなり、その下宿に転がり込んできたのです。そして、「面倒をみてやるから、おまえも入れ」と一緒に住んでいたら、転がり込んだKがまた、そのお嬢さんに恋をするようになるのです。
そこで、Kが「おまえはあのお嬢さんが好きか」と「先生」に訊くと、「いや、そうでもない」という返事です。「そうか・・・」と、またKは悶々としています。
しかし、あるとき「先生」が、がまんできずに、お嬢さんに求婚してしまうのです。すると未亡人のほうから、「よござんす。差し上げましょう」とOKが出るのですが、後でKがそれを聞いてショックを受け、自殺してしまいます。
Kの自殺の後、もちろん「先生」とお嬢さんとは結ばれて結婚するのですが、子供もなく、暗い日々を送ります。やがて、明治天皇が崩御し、乃木将軍が殉死したのを聞いて、「先生」は自分も死んでしまいます。そして、遺書を主人公の青年に託しました―。
このような簡単なストーリーです。
これはこれで、昔は、青春の葛藤、恋の葛藤というように捉えていたのですけれども、今、それをテレビで観てみると、いろいろなことに気がつくのです。お寺の息子であるKという青年について、昔は「死んだ人を悪く言ってはいけない」というぐらいの気持ちしかなく、「純粋だったのだな」と思っていたのですが、いま観てみると違うのです。
先ほど、心の五毒について述べましたが、まず「貪」、貪欲なところがあります。自分は親に勘当されていて経済的基盤もない。それで友人に経済的援助を受けて下宿に入れてもらった。そんなに金もないし、親から勘当されているし、学業もまだ達成できていないにもかかわらず、そこのお嬢さんに恋をして、結婚したいなどと言いはじめた。これは「貪」です。一種の貪欲さです。男性たるもの、経済的自立、社会的確立なくして結婚しようというのは、やはり十年早いのです。お寺の子供であって、仏道修行をしているような雰囲気をにじませながら、実はそういう貪欲があるのです。
それから「瞋」、怒りがあります。友人が自分を出し抜いたということに対して、自殺という行為によって報復するわけです。これは、自分はそれでいいかもしれませんが、自殺された側であるお十さんや友人に対して不幸な影を投げかけ、ある意味では憑依霊になって一生つきまとうわけですから、この怒りというものも正当な怒りではありません。それは自分が愚かなゆえに起きたことであって、やはり不当な怒りだと思います。
それから「癡」があります。あまり賢くありません。学生時代に下宿に入って、たまたまそこにきれいなお嬢さんがいて結婚したくなるというのは、これはもはやミミズに飛びつく魚と同じような本当に単純なことであって、やはり世間知らずの一言に尽きるわけです。社会に出て活躍すれば、まだまだいくらでも自分に合った女性はいるわけです。また、当会の教えを学んでいれば、光明思想や常勝思考など、いくらでもあります。そういうことを知らないで、「寺の僧侶だから自分は悟っているのだ」といような生悟りの気持ちを持っていました。しかし、本当の意味での智慧を持っていなかったのです。そういう「癡」があります。
それから「慢」もありす。「先生」のほうには、自己批判をして自分自身をいじめるような自虐的な気持ちがまだまだありますが、自殺したK自身には、「お寺の子として育ち、精神的に一途に生きている人間であって、そういう欲に振りまわされるような人間ではない」というような自己規定があるのです。そういう自分が簡単に敗れてしまったものだから、生きていられなくなって自殺に走るのです。こういうところに、やはりひとつの「慢」があるように私は思います。
それから「疑」、疑問です。友人に対する疑い、お嬢さんや奥さんに対する疑い、それから親に対する疑い、世間に対する疑い・・・。心のなかは、もう疑いでいっぱいだったろうと思います。「すべてのものが、隠れたところで、自分を迫害するように動いている」と思うのです。
ただ、Kがストレートに下宿のお嬢さんに結婚を申し込んだら受けてもらえたかどうか考えてみると、おそらく蹴られたに違いありません。なぜならば、Kは親に勘当され、経済力も無く居候(いそうろう)している身であって、結婚を申し込んでも受けられるはずがないのです。それにもかかわらず、「友が裏切ったかもわからない」「他の人がどう考えていたのだろうか」と、いろいろなことを考えているうちに悶々(もんもん)となってくるわけですが、ここに「疑」があるのです。
要するに、「貪・瞋・癡・慢・疑」の五つをすべて満たしているのです。そして、自殺に至ったわけですが、当然、地獄に堕ちて不成仏です。しかし、地獄に堕ちて不成仏になったその原因は、自分がつくっているのであって、これから脱却しないかぎり天上界には上がれません。それは、友だちのせいでも、その奥さんになったお嬢さんのせいでもなく、本人自身の問題です。
地獄にはこんな人が大勢いるのです。他人のせいにして、あるいは自分自身のことを解決できないまま死んだ人がたくさんいます。やはりそれは乗りきっていかなければならないことであり、それができないのは、自分の弱さ以外の何ものでもありません。あるいは無明そのものなのです。”明かりが無い”という状態そのものです。それを知らなくてはなりません。
一方、お嬢さんを手に入れて結婚した「先生」のほうは、子供もできず暗い人生を送って、最後には自殺して死ぬわけですが、この人を観てみるとどうでしょう。貪欲かといったら、それほどでもありません。ごく正常だと思います。それから、怒りはどうでしょうか。自分に対する怒りは多少は持っていますが、それほど強く持ってはいません。また、愚かかといえば、愚かでもありません。教養のある人です。れそから「慢」、慢心があるかといったら、慢心もありません。そのかわり、最後の「疑」があるのです。自分に対する疑い、他人に対する疑い、それから、親が死んだときに叔父に騙されて財産を奪われたという疑いがあります。人間不信です。この「疑」の部分があります。この「疑」の部分が、結局、また自己不信にも・
・
�
�
�
�
�って、最後の自殺にもつながったのだろうと思います。
真理的に見ると、夏目漱石の『こころ』に出てくる主人公のふたりは、ひとりは五つの項目のすべてに引っかかっていて、もうひとりは一ヵ所で引っかかっています。このような違いがあるということが、わかってくるようになるのです。
このように、人生にはさまざまな悩みがありますが、ほとんどが無明に起因するものです。無明から脱却するためには、結局、何をする必要があるかというと、自分の身の回りに起きることについて解決していくだけの力を持たないと、本当の意味で知識が智慧になっていないというわけです。
ただペーパー上の○×で百点を取れる人は大勢います。それは、記憶力がよければ、あるいは時間をかければできることです。しかし、それを実体験で、自分の生活で生かしきれるかどうか、これが鍵なのです。これを体得しきれないかぎり、本当の意味で無明からの脱却はしていないと言えると思います。
この話を参考にして、各人が自分の問題を解いていただきたいと思います。
【大川隆法『悟りの挑戦(上巻)』第2章「無明からの脱却」より抜粋】
*・゜・*:.:*・゜・*:.:*・゜・*:.:*・
さて、ここからは、幸福の科学の基本書3部作『黄金の法』を通して、エル・カンターレの歴史観を共に学んでまいります。『黄金の法』は、光の菩薩たちが主の悲願である地上仏国土ユートピア建設のためにどのような活躍をなしたのかを記すものです。人類の歴史に隠されていた地球神を、光の天使・菩薩たちはどのように実行したのか、その一端を学びます。経典をお持ちでない方は、是非この機会に拝受ください。【税抜2000円】
『エル・カンターレが観た歴史観であるとともに、エル・カンターレが立案したところの、地球的仏法真理の大河の鳥瞰図でもあります』(「『黄金の法』まえがき」より)
*・゜・*:.:*・゜・*:.:*・゜・*:.:*・゜
第4章 太陽の昇る国
10 日蓮吼(ほ)ゆ
鎌倉時代の仏教僧について、いろいろと述べきましたが、日蓮(一二二二年~一二八二年)を抜きにしては、鎌倉仏教は語れません。
日蓮は、安房国(あわのくに・千葉県)は小湊の人で、十二歳のときに清住山に登り十六歳で受戒し、蓮長と称し、浄土教を学びました。そのご、鎌倉、比叡山で天台恵心流を修学します。そして、多くの仏典を読破するのですが、とくに、天台大師、最澄の影響を深く胸に刻みました。【※その後の霊査で、日蓮は、現代に、大川直樹さんに転生しています】
一二五二年、清澄寺に帰り、翌一二五三年、仏教の神髄を法華経に見出して、立宗します。しかし、この他宗排撃的法華経至上主義は、寺内の念仏僧と地頭・東条氏の怒りを買い、日蓮は寺を追われることになりました。そこで、鎌倉に逃れます。「念仏無間、禅天魔、真言亡国、律国賊」の四箇格言(しかかくげん)を掲げて、きわめて激しい他宗攻撃を加えて、法華経こそ唯一の正しい法、すなわち、正法であり、この教えに帰依することによって、個人は救われ、国家は平安が約束されるのだとしたのです。
そして、一二五七年頃から一二六〇年頃に、東国に地震、飢饉が相次いだのも、悪法が跋扈(ばっこ)しているからであり、正法に帰依しなければ、内乱外寇によって、亡国の憂き目にあう旨を予言し、『立正安国論』を書いて、北条時頼に上申しました。その結果、幕府は日蓮を伊豆伊東に流したのです。赦免後も、東条氏の襲撃を受け、いっそうの弾圧、迫害を受けます。そして、さらに佐渡に流罪となるのです。しかし、蒙古による外寇が、二度まで日蓮の予言通りだったので、幕府は、その神秘におどろき、怖れ、佐渡流罪の罪を赦しました。(ただし、蒙古によって日本が占領されるという予言は外れました)。日蓮は、この佐渡流罪中に、『開目抄』や『観心本尊抄』を著わし、「南無妙法蓮華経」の題目を唱えることで救済・
・
�
�約束されると説いたのです。
ここで、日蓮の思想と行動を七百年後の真理観の観点から評価してみようと思います。
まず、今日的視点からは、狂信性、排他性、独善性、閉鎖性などの観点からみて、鎌倉時代の日蓮宗が、一種の世紀末カルトであることは否めません。
次に、法華経至上主義についてですが、釈迦の教えは、何百何千の法門(八万四千の法門)があり、法華経のみが正しく、他の経典は真理を伝えていないという考えは、間違っております。各種仏典は、キリスト教の聖書と同じく、弟子たちが筆録し、まとめたものであるわけですから、釈迦の教えをそのままには伝えていなまいことは確かでしょう。法華経も学問的には、釈迦没後、四~五百年後に成立したとする説が有力ですし、晩年の釈迦の教えの一部を反映しているにしかすぎません。結局のところ、各種の経典は、釈迦と弟子たちとの間の、時・場所・人の三者の影響のもとになされた対話の記録であり、どれのみが真実というような性質のものではないのです。
さらに、他宗排撃についてですが、これは功罪の両面があると思います。功の面とは、日蓮宗独自の情熱的な行動力の源泉となった点です。真理が説かれるときは、溢れ出る情熱がなければ、決して広がってはゆきません。真理に到達したという確信が強ければ強いほど他宗が邪教のように思えてくるのは、キリスト教においても同じです。ほんとうは、ひとつの教え、ひとつの真理であるにもかかわらず、さまざまな人によって、さまざまに説明をされると、魂の幼い人々は、異なったものであるかのごとく錯覚して、分からなくなってしまいます。つまり、祖師と違って、弟子たちは、その部分しか理解できないからです。
ですから、空海の真言密教も、親鸞の真宗も、道元の禅も、日蓮の法華経も、それぞれ仏教の法門のひとつにしかすぎないということなのです。つまり、そもそもの釈迦の教えには、すべてが含まれていたのです。釈迦の思想の全体像については、私の『悟りの挑戦』(上・下)、『沈黙の仏陀』『太陽の法』『仏陀の証明』(以上、幸福の科学出版刊)などを読んでいただけば、「南無妙法蓮華経」の題目だけ唱えておれば救われるとする日蓮の考えが、仏陀の本心に反しているには、言うまでもないことでしょう。ともあれ、日蓮の他宗排撃は、真理流布に急であった面は評価できますが、他宗を正邪の「邪」としたのは、間違っております。親鸞も、道元も、日蓮同様の高級霊だからです。
さて、日蓮の思想と行動を理解するにあたっては、その木が実らせた果実をもって検討すべきでしょう。現代には、日蓮正宗の在家信徒団体を詐称する(すでに本山からは破門されている)創価学会という邪教団がはびこっております。この団体は、その発祥において間違いがあります。事実上の初代ともいえる二代目会長、戸田城聖が、自己の事業の経営破綻の急場しのぎに、題目だけ唱えれば、よいとする日蓮宗の弱点につけ込んで布教活動をやったところ、思いのほか資金が集まりました。そして、その味が忘れられず、サラ金屋から宗教屋に乗り換えて出発したのです。戸田の手代だった池田大作の代になってからは、さらに拝金事業体質が強化され、「世界平和」という新しいお題目のもとに、宗教として大石寺本山、政治とし・
・
�
�「公明党」を利用して、利益共同体をつくりあげました。しかし、その本質は、タクシー業者が、節税対策のため、観音像を建てて宗教法人化した事例などと同じです。
「上求菩提」を捨てて「下化衆生」の道を選んだ日蓮の思想が、「慈悲」から「堕落」へと変質するには、深い理論を必要としませんでした。創価学会の会員が、創価学会を批判する人たちに対して、盗聴、尾行、脅迫、無言電話から始まって、犬をけしかけたり、蛇の死骸や鳥の死骸、血だらけの肉や魚を投げ込んで、仏教徒として恥ずかしいと全く感じないのは、「南無妙法蓮華経」だけを唱えておれば仏になれるとする、都合のよい免罪符があるからでしょう。彼らには戒律も反省も無縁なのです。
日本の仏教は、日蓮以降、傑出した僧侶を出していないとも言われます。しかしその現実は、念仏や題目を唱えるだけで救われるという思想が蔓延し、釈迦の教えの中核である「悟り」と、それに伴う「智慧」の立場が顧みられなくなり、ご利益主義や洗脳的狂信思想が現代まで流れつつ、広がっているからです。
日蓮主義が安易な政治的イデオロギーとして利用される時、マルクス主義との差異はほとんどなくなります。目的のためには手段を選ばぬマルクス主義が、暴力主義や粛清へとその軌跡を描いたように、題目さえ唱えておけば何をしてもよいとする、転落型天台本覚思想は、政治勢力と一体化した時、狂信的全体主義へと姿を変えることでしょう。
創価学会員によって、全国民が、盗聴、尾行、密告をされ、理不尽な投獄をされるような未来社会は拒否したいものです。会話のたびにテーブルの下の盗聴器を調べなければならない、かつてのソ連のような暗黒社会の到来は、なんとしても避けたいものです。
やはり、悟りの智慧の立場を堅持しなければなりません。
【大川隆法『黄金の法』第4章「太陽の昇る国」より抜粋】
*・゜・*:.:*・゜・*:.:*・゜・*:.:*・゜
幸福の科学は、この地上に真のユートピアを建設するために、日夜努力しています。私たちが「正しき心の探究」として「愛・知・反省・発展」の四正道の教えの実践と四正道の全世界への布教に向けて伝道しているのは、「仏国土ユートピア建設」のためです。
ここからは、経典『正しき心の探究の大切さ』第1章「未来へ」より教えをいただきます。
*・゜・*:.:*・゜・*:.:*・゜・*:.:*・゜
■『正しき心の探究の大切さ』第1章「未来へ」
〇伝道の原点は、「四正道」を簡単に伝えること
では、何を伝えてほしいかというと、原点に返れば、「愛・知・反省・発展」の「四正道」です。まず、「四正道を、どれだけ簡単に伝えられるか」ということが原点になります。
①いちばん最初に説かれている「愛の教え」
みなさんが伝道する際、おそらく、相手から、「幸福の科学の教えは何ですか」と訊かれるでしょう。そのときには、例えば、次のように話してみてください。
「幸福の科学では、いちばん最初に、『愛の教え』を説いています。『人を愛しなさい』と言っています」
「ああ、それは、よく聞いています。キリスト教でも言われているし、仏教では、『慈悲』なども説かれているから、まあ、そういうことでしょう?」
「そのとおりです。『人を愛しなさい』という教えです」
「では、『人を愛しなさい』とは、どういうことですか」
「それは、『人に優しくしなさい。親切にしなさい。人を思いやりなさい。相手の立場を考えて、ものを言ったり、行動したりしなさい。人のことを考えて生活しなさい』ということです。これが『愛の教え』なのです」
簡単に言えば、こういうことです。
【大川隆法『正しき心の探究の大切さ』第1章「未来へ」より抜粋】
*・゜・*:.:*・゜・*:.:*・゜・*:.:*・゜
続きまして、経典『幸福の科学とは何か』より、与える愛について学びを深めます。
*・゜・*:.:*・゜・*:.:*・゜・*:.:*・゜
〇与える愛と執着
さて次に、「与える愛と執着」について、話をしてみたいと思います。
仏教においては、古来より、愛という言葉を積極的にはとらえておりませんでした。この愛という言葉が、とくに日本において認められ始めたのは、おそらく明治以降であったでしょう。キリスト教が入ってきたのは今から五百年ほど前ですが、その頃にも愛という言葉は使われていなかったはずです。「親切」という言葉で表されていたと思います。こうしてみると、キリスト教でいう愛を「親切」という言葉で表してみるとするならば、そこには仏教とは何らの矛盾がないことが、発見されるのです。
仏教の根本は慈悲であり、多くものたちを慈しむという気持ちが、その出発点にあります。万象万物を慈しむ。動物であっても、食物であっても生あるものを慈しむ。また、生あるものの最もたるものである人間、この他者の存在を祝福し、そして彼らの苦しみを我が苦しみとして考える。これが慈悲のあり方でした。そうした慈悲のあり方は、おのずから他人に対して親切にならざるをえなかったといえましょうか。この意味において、愛も慈悲も、その言葉の使い方さえ注意すれば、根本的には違ったものでないとも言えましょう。
ただ、仏教において、なぜ愛が問題であるとされたかというと、それは、愛というものを煩悩の範疇においてとらえていたからなのです。すなわち、悟りを妨げるものとしての執着のひとつとして、愛が考えられていたのです。
これは、釈尊その人自身の生き方とも関係していたと言えましょうか。この釈迦時代の愛の考え方は、親子の愛、妻と夫との愛、こうしたものが中心であったと言えましょうか。この釈迦時代の愛の考え方は、親子の愛、妻と夫との愛、こうしたものが中心であったと思います。そうすると、釈迦の時代においては、王家に生まれてその跡継ぎにならねばならないというような、この親子の葛藤、また、幾人もの妻との愛情劇、また愛憎劇とも言うべきものが展開されていた、そうした人間関係のしがらみのなかで、どうしても悟りを開けなかったという現状があったのです。それゆえに、釈迦は、この愛というものをひとつの束縛と考え、これを脱しないかぎり、真なる解放、解けということはない、つまり悟りということはないと考え・
・
�
�いたのでした。
これは、たしかにそうした面はあるでしょう。妻子を養うということ、親兄弟がいるということ、これらが真理の道に突き進むための障害になるというのは、いつの時代にもあることです。そして、それがまさしく障害になるのは、彼らへの思いやりや、また慈しみが深ければ深いほど、それが障害になりがちであるとも言えるでしょう。
けれども、ここでもうひとつ考えねばならないことは、環境を乗り越えるという努力の余地はあるということです。現に自分を縛るものがあるからと言って、そのものをいつまでも縛りとだけとらえているのでは、孤高の人として閉じこもっていく以外に道がないのではないでしょうか。そうではなくて、本当の意味で回りを強化していく、その強化の努力の過程において、縛りは解け、お互いに本当に開放的に生きることもできたのではないでしょうか。
すなわち、愛と執着との混同、これはまだまだ自己確立ができていない段階で起きる問題と言えましょう。ほんとうの意味において悟りを開き、そして愛の器量が大きくなった人にとっては、執着の鎖はその人をつなぎ止めることができなくなっていくのです。そのようにして、おのずと家族にも、あるいはその周りの者へも感化がおよび、そして、彼らをも自然のうちに導かざるをえなくなってゆくのです。
しだかって私は、キリストが「預言者故郷に入れられず」という言葉で語っていたことと、釈迦の事象とを比べてみても、真の悟りは、逆に執着を取り除き、与える愛を復活させるものだと考えています。たとえ親であろうとも、兄弟であろうとも、妻であろうとも、子であろうとも、真の悟りを開き、その悟りを押し広げんとしている人に接した場合に自然に道を開いていき、よき協力者となるのではないかと思います。
それゆえ、与える愛というものは、縛りの愛、執着の愛、煩悩の愛とはまったく違ったものだとして分けてとらえるのは、やはりまちがっていると思います。愛のなかには、本質的に同じものもあるけれども、その方向性に違いがあるということです。より多くの人間のために役立つ方向で、その愛のエネルギーを使ったときに、本来執着の愛とか、与える愛とか言うような二分化は起きないのであり、愛は一元となってゆくのです。
【大川隆法『幸福の科学とは何か』第4章「愛の基本」より抜粋】
*・゜・*:.:*・゜・*:.:*・゜・*:.:*・゜
伝道の原点は、「四正道」を簡単に伝えることであることを本日学びしまた。
これは大切な点です。
経典『地獄の法』の第五章「救世主からのメッセージ」では、
「正しき心の探究」としての「現代の四正道」を実践することをの大切さが説かれています。
主におかれましては、「信仰心を持って生きることを、大きな意味において『正しき心の探究』といいます。そして、その『正しき心の探究』の中身とは何であるかといえば、「愛・知・反省・発展」という「現代の四正道」に、今は集約されています」と説かれています。
そして、経典『「正しき心探究」の大切さ』では、
『(伝道において)では、何を伝えてほしいかというと、原点に返れば、「愛・知・反省・発展」の「四正道」です。まず、「四正道を、どれだけ簡単に伝えられるか」ということが原点になります』と説かれており、伝道において、「四正道」分かりやすく伝えることが大切である、と教えていただいています。
本日の引用では、「愛」の教えを分かりやすく伝えるために、愛をこのように定義していたただきました。
『それは、『人に優しくしなさい。親切にしなさい。人を思いやりなさい。相手の立場を考えて、ものを言ったり、行動したりしなさい。人のことを考えて生活しなさい』ということです。これが『愛の教え』なのです』
また、愛一元の考え方として、与える愛と執着について教えていただきました。とても難しい問題ですが、このように教えていただきました。
『愛と執着との混同、これはまだまだ自己確立ができていない段階で起きる問題と言えましょう。ほんとうの意味において悟りを開き、そして愛の器量が大きくなった人にとっては、執着の鎖はその人をつなぎ止めることができなくなっていくのです。そのようにして、おのずと家族にも、あるいはその周りの者へも感化がおよび、そして、彼らをも自然のうちに導かざるをえなくなってゆくのです。・・・
それゆえ、与える愛というものは、縛りの愛、執着の愛、煩悩の愛とはまったく違ったものだとして分けてとらえるのは、やはりまちがっていると思います。愛のなかには、本質的に同じものもあるけれども、その方向性に違いがあるということです。より多くの人間のために役立つ方向で、その愛のエネルギーを使ったときに、本来執着の愛とか、与える愛とか言うような二分化は起きないのであり、愛は一元となってゆくのです』
今日も、神から頂いた無尽蔵の愛を、見返りを求めることなく、隣人に愛を与えるために、『人に優しくしなさい。親切にしなさい。人を思いやりなさい。相手の立場を考えて、ものを言ったり、行動したりしなさい。人のことを考えて生活しなさい』という言葉を胸にこの奇跡の一日を主に捧げてまいります。
本日も愛と天使の働きをなすために、そして私たちの隣人を助けるために、主の教えと信仰心の大切さを伝え、入会・三帰へと導いてまいりましょう。そして、私たちは、人の不幸を呪うのではなく、人の幸福を祈る者になりましよう。
*・゜・*:.:*・゜・*:.:*・゜・*:.:*・゜
本日も、皆様とともに主の新復活を祈り続けてまいります。
*・゜・*:.:*・゜・*:.:*・゜・*:.:*・゜
Lord EL Cantare is my All. 主こそ私のすべて。
We are One, with our Lord. 我々は主と共に一体である。
One for All. All for The One. 一人は主のため、隣人のために。みんなは主の悲願のために。
*・゜・*:.:*・゜・*:.:*・゜・*:.:*・゜
■□■□■□■
。゜+. With Savior 。゜+.
100%エル・カンターレ信仰
―天御祖神とともに―
伊勢から世界に伝える強い信仰
■□■□■□
E-mail:ise@sibu.irh.jp
□■□■□
https://hsise.com/
□■□■
TEL:0596-31-1777
■□■
FAX:0596-31-1778
□■
文責:蒲原宏史
■
(9/17-1)【基礎教学通信】260【9月17日】幸福の科学入門40『正しき心の探究の大切さ』伝道の原点は、「四正道」を簡単に伝えること―「悟りの挑戦(上巻)」『こころ』にみる五毒―『黄金の法』日蓮吼ゆ
 幸福の科学入門
幸福の科学入門